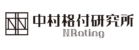懐かしい同僚
中村格付研究所が設立されてもうすぐ一月。先日「パイセン、元気っすか?」というフランクなメッセージをもらった。彼女は、英国系信用調査会社に勤務していた当時の同僚で、私よりも前から勤めていた先輩という事になる。業界に詳しい人ならご存じかも知れないが、我々には「イナガキサン」という共通の敵がいて(笑)、常日頃、愚痴をこぼしながら一緒に仕事をさせてもらったのが懐かしい。
しばらくすると、彼女は英国系信用調査会社を退職したのだが、その後のキャリアは「飛ぶ鳥を落とす勢い」という表現では足りない程、輝かしいものであった。私がようやく平取締役になった頃、既にとあるVC会社のCOOに就任していた。現在は自身の企業投資会社を興し、文字通り大活躍されている。
「パイセン、元気っすか?」から続く会話は、自分にとっても信用調査に応じるとは何かを振り返る良い機会になった。つまりは、その元同僚が経営する会社に、イギリス系ファンド関連の信用調査機関と、国内最王手の信用調査会社から取材の依頼があったが、応じるべきか?という質問をもらったのだ。
ガラパゴス化した国内企業信用調査
クレジットビューロに関するブログでも少し触れたが、日本の企業信用調査と世界の多くの国々のそれには、大きな違いがある。日本の企業信用調査では、信用調査会社の調査員の力量が調査報告書の充実度合いに大きく影響する。これの根本的な原因になっているのが、被調査先経営者(場合によっては部長等の管理職)との対面によるインタビューを取材の大前提にしている事にある。
MBA保有者や中小企業診断士資格取得者などが企業経営分析を行えば、恐らくかなり多くの信用調査会社の調査員よりもレベルの高いアウトプットが出せるのだと思う。しかし、決算書や裁判記録を始め、法人に関する情報開示が他国に比べて極度に遅れている日本においては、彼らの経営分析スキルを活かせるような情報が集まらない。
この点、東京経済という信用調査会社は並外れた調査力を誇り例外であるが、一般的には調査員がいかに被調査先との会話を盛り上げて、直接情報を引き出すことができるかが日本の「信用調査報告書」のエッセンスになっている。
加えて、日本企業の信用調査報告書は、調査担当者による文章による説明が多く、読み物として定性情報が網羅されている。しかし、怪しい会社や継続リスクが高い会社について「危ない会社」と書く事は厳禁されており、「文章によってそれを匂わす」「行間を読ませる」などという、摩訶不思議な慣習があるのも興味深い。
海外の企業信用調査
仕事柄、海外の信用調査業界の人間と話すことも多いが、「日本ではなんで被調査先に直接取材なんかするんだ?」という質問を嫌というほど聞く。直接公開された情報は、その会社にとって都合の良い情報であり、その裏付けが取れない限り信用すべきではない。というのが彼らのロジックだ。だがそもそも、「信用調査会社に虚偽の情報を提供してはいけない」という文化は、1800年代にDun&Bradstreetの創業者が創り出したものなはずだが、話がこじれるので脇に置いておこう。
街の境界線を一歩跨げば外国があるという欧州の地理的条件が寄与し、貿易保険や(海外)企業信用調査という制度が大きく発展してきた訳だが、そうした歴史の中で培われてきたのが、クレジットビューロという制度である。今では三大クレジットビューロというと、英国Experian、米国Trans Union、カナダEquifaxを指し、どちらかというと米国よりのイメージがあるが、金融機関だけにしかビューロへのアクセスが許可されていないのは、世界でも日本くらいだ(と思う。)。
この制度により、A社がB社にものを販売した時、B社はA社にお金をちゃんと払ったか?というデータが幾千億も蓄積され、その他裁判記録や担保設定記録など、充実した行政当局が公開するデータベースと組み合わせ、直接取材による信ぴょう性に乏しい情報に基づかなくとも、企業信用度の判定ができるというのが、世界の潮流である。
格付とPD
そうした取材型レポートと、データ型レポートの違いは、企業信用評価についても違った尺度を生み出している。
日本型の取材型レポートでは、対象企業の格を見る。社会的信用性とでも表現しようか。他方データ型中心の欧米圏では、倒産確率やデフォルト(債務不履行)の可能性を統計学的に分析し、予測値(Probability of Default)としての性格を持つ。街中のパン屋など、規模が小さいと格付評価では高リスクとして評価されるが、予測値では現金商売であるパン屋は、資金繰り難に陥りにくいという傾向を読み、低リスクとして評価されるような格付評価と真逆になるケースもある。
本題
さて、本題。信用調査会社の取材に応じるべきか?
日本においては、これまで説明してきたとおり、企業情報を収集する為の手段はインタビューに大きなウエイトを置いている。その為、インタビューによって自社の情報を開示しない限り、依頼者に対して自社の正しい情報が伝わる可能性は極めて低くなる。「別に、うちの事調べるようなところとなんて、取引しなくてもいいんですよねー。」とは、自分が調査担当だった時もよく言われた断り文句。
けどそこで、依頼者が誰なのか?という点に少し想像を巡らせてみて欲しい。
このブログでは、反社だとか逮捕者だとか、センセーショナルなストーリーばかり書いてしまっているが、信用調査の対象となる企業は、歯をくいしばりながら頑張っているごく一般的な企業だ。ガバナンス等々の理由により、依頼者側も信用調査を行う事が社内の業務ルールになっている為、通常業務の一環として信用調査依頼が発生するのが大方である。
想定依頼者その1 既存の取引先、または新規取引先
そうした業務的に発生した信用調査の依頼であっても、自社の情報公開を断った場合、信用調査会社は集める事ができた情報のみで調査報告書をまとめる事となる。一般的に、調査拒否=後ろめたい事がある という思考バイアスが働く為、取材を拒否した自社にとっては不都合なトーンで報告書が書かれると認識しておくべきだろう。
そのバイアスが効いた調査報告書を受領した依頼者は、本当は優良な会社であっても、割り引いて与信判断することなる。あまり良い情報が書かれていないとすれば、取引条件の絞り込み=前金取引になったり、これまで100万円まで掛けで仕入れが可能だったものが、50万円までになってしまったりと、自社にとってマイナスに作用する事が多い。
なお、クレディセイフ企業情報の日本企業調査の場合、取材協力した際に、自社データがもらえる。自分の会社に対するスコアの根拠なども聞ける為、第三者が自分の会社をどう見ているのか知りたいという事で、進んで自社データの更新を依頼する会社もあるそうだ。
想定依頼者その2 金融機関・リース
想定依頼者その2の場合も、答えない事のデメリットしか想定できないのではないだろうか?その1の場合と同様に、少ない情報での信用調査報告を得た金融機関は、当然ながら融資の実行に際し慎重にならざるを得ないし、優遇された金利が提示されることも少なくなってしまうだろう。新しいコピー機のリース契約も結べないかも知れない。
想定依頼者その3 競合他社
とはいえ、何でもかんでもオープンにすれば良いというものでもない。社内で進んでいる新商品の企画に関する事や、新しく獲得したお客様の話など、依頼者が競合他社だった場合、みなさんのそんな話が聞けるのを固唾を呑んで待っているかも知れない。競合他社の場合、信用調査依頼の際に「この新しい商品をどこに販売しているのか」「この商材の仕入先はどこなのか、必ず聞け」などという指定が入る場合も多く、余計な事は口にしない事だ。
上のようなところから、競合他社に情報が筒抜けになってしまうのはよろしくない訳だが、それ以外自社の情報を信用調査会社に公開する事によるデメリットは少なく、むしろ円滑な与信取引、適正な与信判断を可能にするという意味から、メリットの方が大きい。(なお、信用調査報告書は、意思決定に際しての材料の一部として使われるもので、信用調査の結果が悪い=100%取引停止というものでもない)
私の尊敬して止まない牟田園先生は、与信管理担当者として、被調査先に牟田園先生の会社が信用調査を入れたので、きちんと取材に対応するようにと啓蒙されてきたそうだ。それによって、円滑な取引を可能にする信用調査会社に情報を出すことで、業界全体の社会性が向上する事の重要性に気付いてもらったり、自社について語る事ができる社長を育てる事により、その社長の中での経営ポリシーを磨いていく材料にしてもらったりと、業界に対する教育の材料として信用調査そのものを使われてきたそうだ。
「そりゃちゃんと答えたほうがいいよ!」元同僚には、上のようなところを説明。
「聞いてよかったっす!ちゃんと対応するようにしまーす♡」という返事がもらえた。